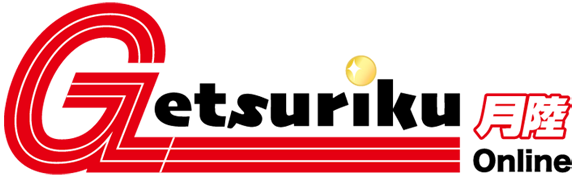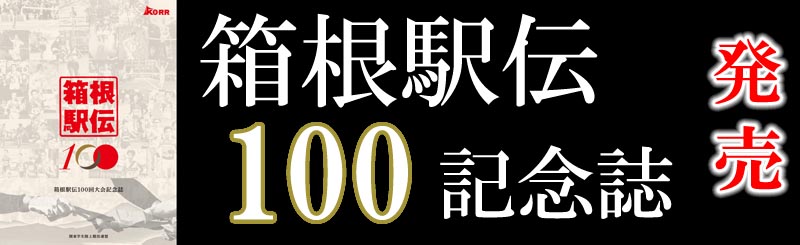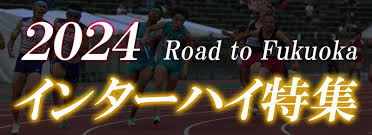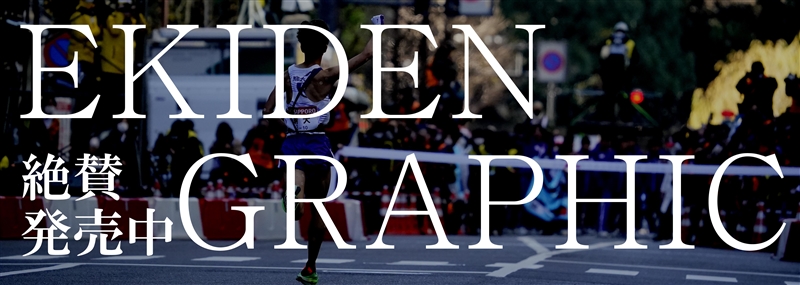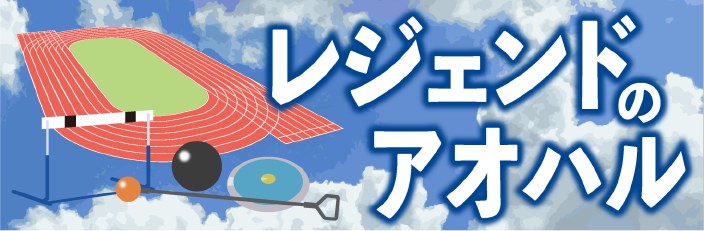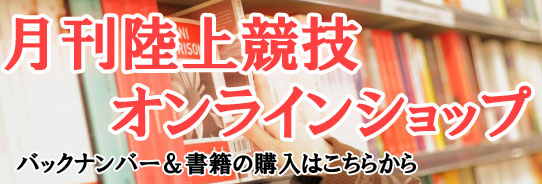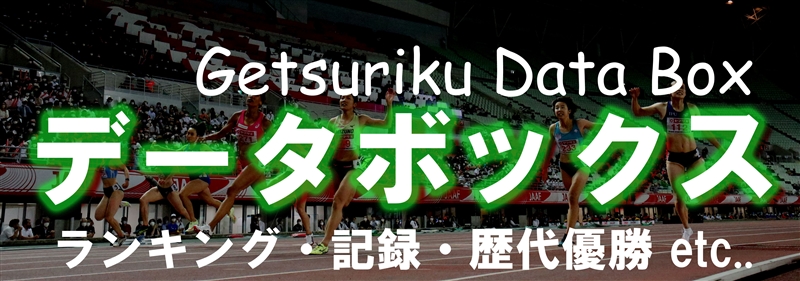「ピンなしスプリントシューズ」メタスプリント開発秘話
アシックススポーツ工学研究所の担当者が語る
アシックスが長年開発してきたスプリントレース用シューズ「METASPRINT TOKYO(メタスプリント トウキョウ)」が3月末に発表された(発売は6月12日)。これまで陸上競技の試合で使われてきたスパイクシューズとは違い、ピンの代わりにハニカム形状(※蜂の巣のような六角形の集合体)の突起がついたカーボンプレートで地面をグリップする構造だ。同社の研究によればスパイクシューズよりも100m換算で約0.048秒速く走れるという。
従来の常識では考えられないスプリントシューズはどのようにして誕生したのか、開発を担当したアシックススポーツ工学研究所の高島慎吾氏と小塚祐也氏にその裏側を語っていただいた。

ピンのないスプリントレース用シューズ「METASPRINT(メタスプリント)」を開発したアシックススポーツ工学研究所の小塚祐也氏(右)と高島慎吾氏
スパイクピンの存在は「制約」だった
これまでスパイクシューズにピンがあるのは当たり前のことだった。その「ピン」をなくす――。そんな逆転の発想が生まれたのは、選手へのヒアリングがきっかけだったという。そこから2020年を見据えたまったく新しいシューズの開発が始まった。
――「METASPRINT(メタスプリント)」は、どのような経緯で開発が始まったのでしょうか。
小塚祐也 きっかけは選手に(スパイクの使用感を)ヒアリングしていく中でわかったことですが、従来のスパイクピンの長さや形を選手が自分の好みで選んでいたのです。どうしてそういうことをしているのかと聞くと、ピンの刺さりやすさが違うというコメントが多くありました。そこで我々はピンが刺さったり抜けたりする感覚があるということは、そこに時間のロスがあると考え、その時間をなくすことができれば、より速く走れる靴ができるんじゃないかということで2015年から開発がスタートしました。
――今まであったはずのピンをなくすというのは、どういう着想から生まれたのでしょうか。
高島慎吾 ピンがなくてもあまり滑らないというのは、わりと初期の段階でわかったんです。六角形のおろし金のようなアルミのシートがあるのですが、それをカーボンのソールに貼って走ってみると、あまり滑らなかったんです。これはいけるということで、ピンがない構造に着手したのですが、単純にピンをなくすだけだとおもしろくないので、「ピンをなくすことでしかできないものにしたい」というのがありました。
ピンは(陸上競技のルールで)11本以内しかつけられない。ピンは金属ですので、ソールに対して垂直のものしかつけられません。それは制約だと考えました。しかし、プレートを複雑な立体形状にすれば、11本までという制約もなくなります。そこで、必要な場所で必要な方向にグリップできるように複雑な立体形状を設けようとトライしました。

メタスプリントのプレートにはピンの代わりにハニカム形状の突起がついている
――何パターンくらい考えたのですか?
高島 従来であればこういう製品を作る時は形を描いてモノを作り上げていくのが基本なのですが、これに関しては新しい設計技術にトライしていて、すべて計算式で作り上げていったんです。「ここがダメだ」となるとリアルタイムで形が変わるような技術を使っていまして、パラメトリックデザインと言われるような、コンピュータ上ですべてを設計する新しい技術です。それを使うと短時間でコンピュータが数え切れないくらいのパターンを排出できるため、多くの形に対して検討することができます。
――シミュレーターみたいなことですか?
高島 そうですね。私のほうで形をリアルタイムにいろいろと変えられるような技術を構築しました。もちろん、それだけだと性能がいいかどうかわからないので、小塚さんとタッグを組ませてもらって。
小塚 通常のスパイクはピンを配置するところには当然ピンを固定するための土台があって、そこがすごく硬くなってしまうという課題があったんです。ピンをどこに配置するかでソールの硬さがある程度決まってしまうのですが、ピンのないシューズはそういった制約がすべてなくなるので、我々が理想としているソールの硬さや、(プレートを)どう曲げたいのかという希望も実現できるのです。ただ、性能を確認するために10パターンも20パターンもモノとして実際に作り上げようとすると、作るだけでも時間がかかってしまいます。より早く市場に届けるためには、コンピュータシミュレーションを活用して、いかに短い期間で我々の理想の形にできるかがすごく大事でした。
「1枚のカーボン」がベストだった
設計でコンピュータを活用することで、トライ&エラーの工程は大幅に短縮できた。ところが、実際にシューズを作るとなると、そこには高いハードルが立ちふさがった。
――ピンが刺さるという点では、ピンを短くしたり、ピンと立体構造を併用する手もあったと思いますが、そういったことは検討されましたか?
高島 してないです。研究者という性質上、新しいことをやってみたいという気持ちがあって、中途半端なことをするくらいならなくしちゃえばいいや、と。
小塚 もう1つ特徴的なのが、カーボンという1つの材料ですべてを作り上げているところです。難しい製造技術ですので、立体形状の高さや角度には制約があって、それをしっかり満たしながらグリップなどの性能面も考慮して作りました。
高島 はじめの頃は理想形を作ってしまって、全然モノを作れませんでした。
小塚 デジタルで設計していることもあって、理想とした形が設計できても、それをモノにするためのハードルがすごく高かった。デジタル上での設計技術と製造技術という2つのポイントがあって、両方を進めてきたのがこの新シューズです。
――異なる素材を組み合わせるのではなく、カーボンだけにした理由は?
高島 通常は樹脂のプレートを使うのですが、それだと絶対に(強度が)もたないんですよ。金属のピンでしっかりと地面をとらえているものに対して、樹脂で同じような機能を持たせようとすると、すぐにちぎれたり摩耗してしまったりします。金属に代替できるぐらいに強く、軽いものとしてのカーボンです。カーボンだけでこういった複雑な形状を作り上げるというのを目指していました。逆に言うと、これしか思いつきませんでした。
小塚 プレートをかなり薄くできたので、他のパーツをつけるための固定部を設けるぐらいであれば、カーボン1枚で作ったほうが薄くて軽くできるので、あえて複合しませんでした。
――ハニカム形状になったのはどの段階ですか?
高島 初期の時から構想はありました。過去大会でのスパイク開発の知見から、軽量で強度の高いハニカムサンドイッチ構造が、グリップにも使用できるのではないかと試したところ、滑らなかったんです。
小塚 それが三角形だと特定の方向にしかグリップできないため、いろんな選手の走り方に合った突起を配置できるように、三角形や四角形ではなく、六角形を採用しています。
――全方位に向いてるということですよね。
小塚 そうです。実は場所ごとに突起の高さや角度をちょっとずつ変えています。ピンだと斜めに刺すのはかなりストレスになるので実現できないんですけど、ピンのない構造だと接地角度に合わせて突起自体を傾けることができるため、カーブもスムーズに走れる構造になっています。
――このシューズを履くことの最大のメリットは?
高島 やはりタイムに還元してほしいと思っています。ピンをなくす効果としては、人が地面に伝える力をロスさせないというところがあります。地面に刺さっていく時間もロスですけれど、ピンを抜くにもすごく力を使っています。これを刺さずに走ることができれば、そういったところにも還元できるんじゃないかと思います。
モニタリングを重ねて改良
完成までは40足以上
プロトタイプを作ってからも、完成までには試行錯誤が続いた。このシューズを作るにあたっては男子100mの前日本記録(9秒98)保持者である桐生祥秀(日本生命)の着用テストやヒアリングを繰り返した。そのやり取りの中で40足以上のシューズを製作したという。

室内競技場での60m走でスパイクとの差を検証した

比較実験で使われたのは製品版とは違ってアッパーが白いもの(左)。右が従来のスパイクシューズ
――このシューズを開発する上で従来と違った点は?
小塚 これまでと違ったのは、ピンがない構造というのは初めてだったので、選手が日常的に使った時にどうなるのかを確かめる必要がありました。通常であれば短期のことが多いのですが、今回は長期的な目線で、これで本当に大丈夫なのかを確認するため、選手に長く使ってもらうことを意識しました。
高島 今回はトップスプリンターだけでなく、一般の選手にも届けたいという想いから、多くの大学生にも協力していただき、長く履いていただきました。最初は5足出して全部壊れて返ってきたりして、そういったことを繰り返しました。
小塚 一旦設計を見直すフェーズもありましたが、2018年から今までずっとそれを続けていました。

開発にあたっては関西地区の大学生アスリートにも協力を仰いだ
――桐生選手とはどのようなコミュニケーションを取ってきましたか?
小塚 やはり、桐生選手の感覚は本当に繊細で研ぎ澄まされているので、「1mm高さが変わるだけで接地の仕方が変わってしまう」というコメントがありました。ソールのどの方向にどういった力がかかるかは事前に把握していたので、それをピンのない構造で実現するためにはどういった形がいいのかをヒアリングして、突起一つひとつの高さや形を選手の声も参考にしながら作り上げました。
――それはいつからですか?
小塚 2018年です。初めて9秒台を出した思い入れのあるシューズがピンのあるものでしたから、最初に持って行った時はギャップが大きかったと思います。ヒアリングをしながら完成度を高めていく中で、ようやく世界大会で使ってもらえるようなレベルに持ってこられたかなと思います。
――意見をフィードバックしたのは細かい部分ですか?
高島 こちらの想定と違うところがいくつかありまして、より桐生選手の力の向きに直接的に関わるよう『壁』を配置しています。もちろん、桐生選手自身も進化しているので、ソールの硬さは筋力が上がるにつれて変えていっています。実際に試合で履いてもらうまでには40足以上作りました。
小塚 すごく感覚が研ぎ澄まされているので、厚さがコンマ何ミリ変わるだけで敏感に反応されるんです。そこをシビアに、一つひとつ対応しました。「これが足りない」となれば準備してきて、どんどん履いてもらって。
高島 それを40回繰り返して、やっと気に入っていただけるものになったと思います。
――本人の感想は?
小塚 ピンが刺さる時には時間や力のロスがあるのですが、それがないというのがまず1つ。おもしろいと思ったのが、これを履いてしまうと「ピンがあることに違和感がある」というコメントです。実は、桐生選手は足の裏全体で着地するフラットな着地走法のため、ピンがなくてもいいんじゃないかという話が以前から出ていました。
――履くことでフォームに変化はありますか?
小塚 「接地を意識するようになった」と言う選手がすごく多いです。普段であれば脚が流れていたところが、ピンがないことを意識して走ることで最後に脚が流れにくくなり、タイムにも直結している選手もいます。これをきっかけに走り方の意識を変えられるところが選手にとってポジティブに働くと思います。

ピンがないことで接地が意識しやすくなるという
◎構成/山本慎一郎
<関連記事>
・アシックスが新コンセプトシューズ「METASPRINT(メタスプリント)」と 「METARACER(メタレーサー)」を発表
・ASICSの〝先進的〟レーシングシューズ METASPRINT(メタスプリント)&METARACER(メタレーサー)【PR】
・【シューズレポ】サブスリー編集者が語る!! アシックスのカーボンプレート搭載シューズ「METARACER(メタレーサー)」
・【シューズレポ】サブスリー編集者が語る!! アシックスの厚底シューズ「GLIDERIDE」
<関連リンク>
SUNRISE RED(アシックスの特設サイト)
「ピンなしスプリントシューズ」メタスプリント開発秘話 アシックススポーツ工学研究所の担当者が語る
アシックスが長年開発してきたスプリントレース用シューズ「METASPRINT TOKYO(メタスプリント トウキョウ)」が3月末に発表された(発売は6月12日)。これまで陸上競技の試合で使われてきたスパイクシューズとは違い、ピンの代わりにハニカム形状(※蜂の巣のような六角形の集合体)の突起がついたカーボンプレートで地面をグリップする構造だ。同社の研究によればスパイクシューズよりも100m換算で約0.048秒速く走れるという。 従来の常識では考えられないスプリントシューズはどのようにして誕生したのか、開発を担当したアシックススポーツ工学研究所の高島慎吾氏と小塚祐也氏にその裏側を語っていただいた。 ピンのないスプリントレース用シューズ「METASPRINT(メタスプリント)」を開発したアシックススポーツ工学研究所の小塚祐也氏(右)と高島慎吾氏
ピンのないスプリントレース用シューズ「METASPRINT(メタスプリント)」を開発したアシックススポーツ工学研究所の小塚祐也氏(右)と高島慎吾氏
スパイクピンの存在は「制約」だった
これまでスパイクシューズにピンがあるのは当たり前のことだった。その「ピン」をなくす――。そんな逆転の発想が生まれたのは、選手へのヒアリングがきっかけだったという。そこから2020年を見据えたまったく新しいシューズの開発が始まった。 ――「METASPRINT(メタスプリント)」は、どのような経緯で開発が始まったのでしょうか。 小塚祐也 きっかけは選手に(スパイクの使用感を)ヒアリングしていく中でわかったことですが、従来のスパイクピンの長さや形を選手が自分の好みで選んでいたのです。どうしてそういうことをしているのかと聞くと、ピンの刺さりやすさが違うというコメントが多くありました。そこで我々はピンが刺さったり抜けたりする感覚があるということは、そこに時間のロスがあると考え、その時間をなくすことができれば、より速く走れる靴ができるんじゃないかということで2015年から開発がスタートしました。 ――今まであったはずのピンをなくすというのは、どういう着想から生まれたのでしょうか。 高島慎吾 ピンがなくてもあまり滑らないというのは、わりと初期の段階でわかったんです。六角形のおろし金のようなアルミのシートがあるのですが、それをカーボンのソールに貼って走ってみると、あまり滑らなかったんです。これはいけるということで、ピンがない構造に着手したのですが、単純にピンをなくすだけだとおもしろくないので、「ピンをなくすことでしかできないものにしたい」というのがありました。 ピンは(陸上競技のルールで)11本以内しかつけられない。ピンは金属ですので、ソールに対して垂直のものしかつけられません。それは制約だと考えました。しかし、プレートを複雑な立体形状にすれば、11本までという制約もなくなります。そこで、必要な場所で必要な方向にグリップできるように複雑な立体形状を設けようとトライしました。 メタスプリントのプレートにはピンの代わりにハニカム形状の突起がついている
――何パターンくらい考えたのですか?
高島 従来であればこういう製品を作る時は形を描いてモノを作り上げていくのが基本なのですが、これに関しては新しい設計技術にトライしていて、すべて計算式で作り上げていったんです。「ここがダメだ」となるとリアルタイムで形が変わるような技術を使っていまして、パラメトリックデザインと言われるような、コンピュータ上ですべてを設計する新しい技術です。それを使うと短時間でコンピュータが数え切れないくらいのパターンを排出できるため、多くの形に対して検討することができます。
――シミュレーターみたいなことですか?
高島 そうですね。私のほうで形をリアルタイムにいろいろと変えられるような技術を構築しました。もちろん、それだけだと性能がいいかどうかわからないので、小塚さんとタッグを組ませてもらって。
小塚 通常のスパイクはピンを配置するところには当然ピンを固定するための土台があって、そこがすごく硬くなってしまうという課題があったんです。ピンをどこに配置するかでソールの硬さがある程度決まってしまうのですが、ピンのないシューズはそういった制約がすべてなくなるので、我々が理想としているソールの硬さや、(プレートを)どう曲げたいのかという希望も実現できるのです。ただ、性能を確認するために10パターンも20パターンもモノとして実際に作り上げようとすると、作るだけでも時間がかかってしまいます。より早く市場に届けるためには、コンピュータシミュレーションを活用して、いかに短い期間で我々の理想の形にできるかがすごく大事でした。
メタスプリントのプレートにはピンの代わりにハニカム形状の突起がついている
――何パターンくらい考えたのですか?
高島 従来であればこういう製品を作る時は形を描いてモノを作り上げていくのが基本なのですが、これに関しては新しい設計技術にトライしていて、すべて計算式で作り上げていったんです。「ここがダメだ」となるとリアルタイムで形が変わるような技術を使っていまして、パラメトリックデザインと言われるような、コンピュータ上ですべてを設計する新しい技術です。それを使うと短時間でコンピュータが数え切れないくらいのパターンを排出できるため、多くの形に対して検討することができます。
――シミュレーターみたいなことですか?
高島 そうですね。私のほうで形をリアルタイムにいろいろと変えられるような技術を構築しました。もちろん、それだけだと性能がいいかどうかわからないので、小塚さんとタッグを組ませてもらって。
小塚 通常のスパイクはピンを配置するところには当然ピンを固定するための土台があって、そこがすごく硬くなってしまうという課題があったんです。ピンをどこに配置するかでソールの硬さがある程度決まってしまうのですが、ピンのないシューズはそういった制約がすべてなくなるので、我々が理想としているソールの硬さや、(プレートを)どう曲げたいのかという希望も実現できるのです。ただ、性能を確認するために10パターンも20パターンもモノとして実際に作り上げようとすると、作るだけでも時間がかかってしまいます。より早く市場に届けるためには、コンピュータシミュレーションを活用して、いかに短い期間で我々の理想の形にできるかがすごく大事でした。
「1枚のカーボン」がベストだった
設計でコンピュータを活用することで、トライ&エラーの工程は大幅に短縮できた。ところが、実際にシューズを作るとなると、そこには高いハードルが立ちふさがった。 ――ピンが刺さるという点では、ピンを短くしたり、ピンと立体構造を併用する手もあったと思いますが、そういったことは検討されましたか? 高島 してないです。研究者という性質上、新しいことをやってみたいという気持ちがあって、中途半端なことをするくらいならなくしちゃえばいいや、と。 小塚 もう1つ特徴的なのが、カーボンという1つの材料ですべてを作り上げているところです。難しい製造技術ですので、立体形状の高さや角度には制約があって、それをしっかり満たしながらグリップなどの性能面も考慮して作りました。 高島 はじめの頃は理想形を作ってしまって、全然モノを作れませんでした。 小塚 デジタルで設計していることもあって、理想とした形が設計できても、それをモノにするためのハードルがすごく高かった。デジタル上での設計技術と製造技術という2つのポイントがあって、両方を進めてきたのがこの新シューズです。 ――異なる素材を組み合わせるのではなく、カーボンだけにした理由は? 高島 通常は樹脂のプレートを使うのですが、それだと絶対に(強度が)もたないんですよ。金属のピンでしっかりと地面をとらえているものに対して、樹脂で同じような機能を持たせようとすると、すぐにちぎれたり摩耗してしまったりします。金属に代替できるぐらいに強く、軽いものとしてのカーボンです。カーボンだけでこういった複雑な形状を作り上げるというのを目指していました。逆に言うと、これしか思いつきませんでした。 小塚 プレートをかなり薄くできたので、他のパーツをつけるための固定部を設けるぐらいであれば、カーボン1枚で作ったほうが薄くて軽くできるので、あえて複合しませんでした。 ――ハニカム形状になったのはどの段階ですか? 高島 初期の時から構想はありました。過去大会でのスパイク開発の知見から、軽量で強度の高いハニカムサンドイッチ構造が、グリップにも使用できるのではないかと試したところ、滑らなかったんです。 小塚 それが三角形だと特定の方向にしかグリップできないため、いろんな選手の走り方に合った突起を配置できるように、三角形や四角形ではなく、六角形を採用しています。 ――全方位に向いてるということですよね。 小塚 そうです。実は場所ごとに突起の高さや角度をちょっとずつ変えています。ピンだと斜めに刺すのはかなりストレスになるので実現できないんですけど、ピンのない構造だと接地角度に合わせて突起自体を傾けることができるため、カーブもスムーズに走れる構造になっています。 ――このシューズを履くことの最大のメリットは? 高島 やはりタイムに還元してほしいと思っています。ピンをなくす効果としては、人が地面に伝える力をロスさせないというところがあります。地面に刺さっていく時間もロスですけれど、ピンを抜くにもすごく力を使っています。これを刺さずに走ることができれば、そういったところにも還元できるんじゃないかと思います。モニタリングを重ねて改良 完成までは40足以上
プロトタイプを作ってからも、完成までには試行錯誤が続いた。このシューズを作るにあたっては男子100mの前日本記録(9秒98)保持者である桐生祥秀(日本生命)の着用テストやヒアリングを繰り返した。そのやり取りの中で40足以上のシューズを製作したという。 室内競技場での60m走でスパイクとの差を検証した
室内競技場での60m走でスパイクとの差を検証した
 比較実験で使われたのは製品版とは違ってアッパーが白いもの(左)。右が従来のスパイクシューズ
――このシューズを開発する上で従来と違った点は?
小塚 これまでと違ったのは、ピンがない構造というのは初めてだったので、選手が日常的に使った時にどうなるのかを確かめる必要がありました。通常であれば短期のことが多いのですが、今回は長期的な目線で、これで本当に大丈夫なのかを確認するため、選手に長く使ってもらうことを意識しました。
高島 今回はトップスプリンターだけでなく、一般の選手にも届けたいという想いから、多くの大学生にも協力していただき、長く履いていただきました。最初は5足出して全部壊れて返ってきたりして、そういったことを繰り返しました。
小塚 一旦設計を見直すフェーズもありましたが、2018年から今までずっとそれを続けていました。
比較実験で使われたのは製品版とは違ってアッパーが白いもの(左)。右が従来のスパイクシューズ
――このシューズを開発する上で従来と違った点は?
小塚 これまでと違ったのは、ピンがない構造というのは初めてだったので、選手が日常的に使った時にどうなるのかを確かめる必要がありました。通常であれば短期のことが多いのですが、今回は長期的な目線で、これで本当に大丈夫なのかを確認するため、選手に長く使ってもらうことを意識しました。
高島 今回はトップスプリンターだけでなく、一般の選手にも届けたいという想いから、多くの大学生にも協力していただき、長く履いていただきました。最初は5足出して全部壊れて返ってきたりして、そういったことを繰り返しました。
小塚 一旦設計を見直すフェーズもありましたが、2018年から今までずっとそれを続けていました。
 開発にあたっては関西地区の大学生アスリートにも協力を仰いだ
――桐生選手とはどのようなコミュニケーションを取ってきましたか?
小塚 やはり、桐生選手の感覚は本当に繊細で研ぎ澄まされているので、「1mm高さが変わるだけで接地の仕方が変わってしまう」というコメントがありました。ソールのどの方向にどういった力がかかるかは事前に把握していたので、それをピンのない構造で実現するためにはどういった形がいいのかをヒアリングして、突起一つひとつの高さや形を選手の声も参考にしながら作り上げました。
――それはいつからですか?
小塚 2018年です。初めて9秒台を出した思い入れのあるシューズがピンのあるものでしたから、最初に持って行った時はギャップが大きかったと思います。ヒアリングをしながら完成度を高めていく中で、ようやく世界大会で使ってもらえるようなレベルに持ってこられたかなと思います。
――意見をフィードバックしたのは細かい部分ですか?
高島 こちらの想定と違うところがいくつかありまして、より桐生選手の力の向きに直接的に関わるよう『壁』を配置しています。もちろん、桐生選手自身も進化しているので、ソールの硬さは筋力が上がるにつれて変えていっています。実際に試合で履いてもらうまでには40足以上作りました。
小塚 すごく感覚が研ぎ澄まされているので、厚さがコンマ何ミリ変わるだけで敏感に反応されるんです。そこをシビアに、一つひとつ対応しました。「これが足りない」となれば準備してきて、どんどん履いてもらって。
高島 それを40回繰り返して、やっと気に入っていただけるものになったと思います。
――本人の感想は?
小塚 ピンが刺さる時には時間や力のロスがあるのですが、それがないというのがまず1つ。おもしろいと思ったのが、これを履いてしまうと「ピンがあることに違和感がある」というコメントです。実は、桐生選手は足の裏全体で着地するフラットな着地走法のため、ピンがなくてもいいんじゃないかという話が以前から出ていました。
――履くことでフォームに変化はありますか?
小塚 「接地を意識するようになった」と言う選手がすごく多いです。普段であれば脚が流れていたところが、ピンがないことを意識して走ることで最後に脚が流れにくくなり、タイムにも直結している選手もいます。これをきっかけに走り方の意識を変えられるところが選手にとってポジティブに働くと思います。
開発にあたっては関西地区の大学生アスリートにも協力を仰いだ
――桐生選手とはどのようなコミュニケーションを取ってきましたか?
小塚 やはり、桐生選手の感覚は本当に繊細で研ぎ澄まされているので、「1mm高さが変わるだけで接地の仕方が変わってしまう」というコメントがありました。ソールのどの方向にどういった力がかかるかは事前に把握していたので、それをピンのない構造で実現するためにはどういった形がいいのかをヒアリングして、突起一つひとつの高さや形を選手の声も参考にしながら作り上げました。
――それはいつからですか?
小塚 2018年です。初めて9秒台を出した思い入れのあるシューズがピンのあるものでしたから、最初に持って行った時はギャップが大きかったと思います。ヒアリングをしながら完成度を高めていく中で、ようやく世界大会で使ってもらえるようなレベルに持ってこられたかなと思います。
――意見をフィードバックしたのは細かい部分ですか?
高島 こちらの想定と違うところがいくつかありまして、より桐生選手の力の向きに直接的に関わるよう『壁』を配置しています。もちろん、桐生選手自身も進化しているので、ソールの硬さは筋力が上がるにつれて変えていっています。実際に試合で履いてもらうまでには40足以上作りました。
小塚 すごく感覚が研ぎ澄まされているので、厚さがコンマ何ミリ変わるだけで敏感に反応されるんです。そこをシビアに、一つひとつ対応しました。「これが足りない」となれば準備してきて、どんどん履いてもらって。
高島 それを40回繰り返して、やっと気に入っていただけるものになったと思います。
――本人の感想は?
小塚 ピンが刺さる時には時間や力のロスがあるのですが、それがないというのがまず1つ。おもしろいと思ったのが、これを履いてしまうと「ピンがあることに違和感がある」というコメントです。実は、桐生選手は足の裏全体で着地するフラットな着地走法のため、ピンがなくてもいいんじゃないかという話が以前から出ていました。
――履くことでフォームに変化はありますか?
小塚 「接地を意識するようになった」と言う選手がすごく多いです。普段であれば脚が流れていたところが、ピンがないことを意識して走ることで最後に脚が流れにくくなり、タイムにも直結している選手もいます。これをきっかけに走り方の意識を変えられるところが選手にとってポジティブに働くと思います。
 ピンがないことで接地が意識しやすくなるという
◎構成/山本慎一郎
<関連記事>
・アシックスが新コンセプトシューズ「METASPRINT(メタスプリント)」と 「METARACER(メタレーサー)」を発表
・ASICSの〝先進的〟レーシングシューズ METASPRINT(メタスプリント)&METARACER(メタレーサー)【PR】
・【シューズレポ】サブスリー編集者が語る!! アシックスのカーボンプレート搭載シューズ「METARACER(メタレーサー)」
・【シューズレポ】サブスリー編集者が語る!! アシックスの厚底シューズ「GLIDERIDE」
<関連リンク>
SUNRISE RED(アシックスの特設サイト)
ピンがないことで接地が意識しやすくなるという
◎構成/山本慎一郎
<関連記事>
・アシックスが新コンセプトシューズ「METASPRINT(メタスプリント)」と 「METARACER(メタレーサー)」を発表
・ASICSの〝先進的〟レーシングシューズ METASPRINT(メタスプリント)&METARACER(メタレーサー)【PR】
・【シューズレポ】サブスリー編集者が語る!! アシックスのカーボンプレート搭載シューズ「METARACER(メタレーサー)」
・【シューズレポ】サブスリー編集者が語る!! アシックスの厚底シューズ「GLIDERIDE」
<関連リンク>
SUNRISE RED(アシックスの特設サイト) |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking  人気記事ランキング
人気記事ランキング
2025.04.25
編集部コラム「どこよりも早い!?アジア選手権展望」
-
2025.04.25
-
2025.04.25
-
2025.04.25
-
2025.04.19
-
2025.04.20
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
-
2025.04.01
-
2025.04.12
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.04.25
編集部コラム「どこよりも早い!?アジア選手権展望」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2025.04.25
前田彩花が選考レース10000m1着! ハーフの悔しさ晴らし「余裕持って走れた」/日本学生個人
◇日本学生個人選手権(4月25日~27日/神奈川・レモンガススタジアム平塚)1日目 日本学生個人選手権内でワールドユニバーシティゲームズ代表選考会の女子10000mが行われ、前田彩花(関大)が33分10秒60で1着だった […]
2025.04.25
【選手名鑑】荒井 七海
荒井 七海 ARAI NANAMI SNS: Honda 1994年12月26日 御滝中(千葉)→八千代松陰高(千葉)→東海大 1500m:3.36.63(22年) 5000m:13.36.68(25年) ■代表歴 アジ […]
Latest Issue  最新号
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)