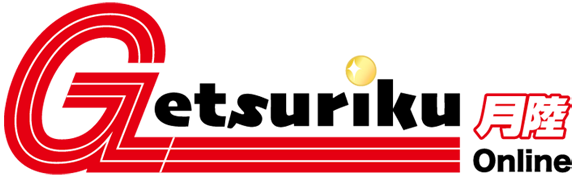2021.08.02

女子やり投の日本記録保持者・北口榛花(JAL)が、東京五輪・陸上競技の5日目の8月3日に登場する。世界基準のポテンシャルを誇る北口。女子ただ1人のフィールド種目代表として目指すのは「1人でも多く倒すこと」。幼い頃から夢見てきた舞台に、日本の大器がついに立つ。
五輪を前に助走のリズム変更
何度も何度もスマートフォンでチェコにいるディヴィッド・シェケラックコーチから出された練習メニューを確認。離れている時はスマホやアプリを使ってコミュニケーションを取る。遠くを見つめるとき、何を考えているのか聞いてみた。
「あー、やりたくないなぁって」
北口はそう言って笑ったあと、険しい表情を浮かべ、フーッと一息ついてからまた走り出す。
2019年のシーズン終了から2度の冬季練習で、短距離ブロック顔負けくらいの時間を走る練習に費やしたという。走り終わったあと、「このメニュー、なんか違う気がする。チェコ語でメニューが出されるから合っているかわからない」とつぶやく。大変そうだけど、なんだか楽しげだ。
やり投選手とは思えない練習メニュー。そういえば、練習で投げているところをほとんど見たことがない。走り終え、クタクタになって、また空を見つめる。女子やり投日本記録保持者は、いったいどこを見ているのだろうか。
2019年の5月に64m36の日本新記録を樹立。いち早く東京五輪の参加標準記録を突破した。その年のドーハ世界選手権に初出場し、決勝まであと6cmまで迫る健闘。悔し涙を流したものの、直後の北九州カーニバルでは“世界基準”と言える66m00と再び日本記録を叩き出した。
普通であれば、この状態でオリンピックへ、となるところ。だが、コロナ禍で東京五輪が延期したこともあり、昨シーズン北口は助走の変更に踏み切った。
「もちろん延期決まったから変えたのもありますが、東京五輪でどうこうということではなくて、66mを投げたあとも『それ以上を投げるためには何かを変えないといけない』という思いはずっとありました」
2019年シーズンは16歩の助走のうち、やりを持ちながら走る「保持走」と、身体を横にして構えに入る「クロスステップ」が、8歩ずつだった。そのリズムを昨年は10歩+6歩に変更。
これまでも助走スピードが大きな課題だった北口は、「スピードを上げるために助走距離を延ばす選択肢もあるとは思いますが、分析データを見るとクロスステップで減速していたので、それならクロスを減らせば減速率を抑えられると思いました」とその狙いを明かしている。
だが、そのフォームは安定感を欠き、ある程度ハマった時は全日本実業団のように63m45をマークできたが、60m台はこの時の2本のみ。日本選手権でも連覇を逃している。

今年に入ってさらに助走を改良
「どうしてもやりを引くタイミングが毎回変わってしまって……。投げの準備に入るまでに遅れることが多かった」と、なかなか感覚をつかめずにいた。
走練習を重ねたことで助走スピードは確かに向上。だが、その反面、特長だった上半身が生かし切れない。もどかしい思いがあった。
そうしたなか、春にはシェケラックコーチがいるチェコへと渡った。コロナ禍でもちろん不安はあったが、東京五輪までにしっかりコミュニケーションを図りたかった。
チェコに着いた北口に、シェケラックコーチは「助走を変えよう」と提案する。足踏みするルーティンも「やめなさい」とストップ。「最初はめちゃくちゃ抵抗しました」と北口は笑う。だが、「私は“投げ”が特長の選手なので、そこを生かすために、投げの“準備”に入るためにクロスステップを8歩に戻しました」と受け入れた。当然、これまでとはまったく違う投げになる。
欧州で3試合に出場して1度も60mを超えられず。「このまま速く走り続けていいのかなって。ヨーロッパの選手よりも助走距離が長くて、走るのが苦手なのになんでこんなに走るの? ってコーチに聞いたりもして。焦りもありましたし、誰を信じていいのか迷いました」。それでも最後は「自分のやってきたことを信じる」と心に決めた。
帰国後、国士大競技会で59m11を投げて気持ちが吹っ切れると、日本選手権では61m49を投げて2年ぶりの優勝。東京五輪代表の切符をつかみ取った。
順風満帆から一転、苦しい日々
北口は幼い頃からオリンピックを夢見てきた。バドミントンやスイミングに励んでいた少女は、「ボランティアでもどんなかたちでもオリンピックに関わりたい」という思いが幼心に芽生えていた。
北海道・旭川東高に進学してから陸上部に。中学時代、北口のバドミントン部の先輩が陸上部のマネジャーになり、当時顧問だった松橋昌巳先生に「こんな子がいます」と推薦したのがすべての始まりだった。
長身と身体能力、肩の強さと柔軟性を見込まれて、やり投の素質はすぐに花開く。当初は水泳と掛け持ちだったが、高1でインターハイに出場。陸上に専念すると、高2でインターハイを優勝し、3年時には連覇した。さらに世界ユース選手権(18歳未満)では世界一に輝いている。
どれだけ直接的な影響があるかはわからないが、北口の特徴でもある肩の柔軟性や強さは競泳やバドミントンとは無関係ではないだろう。さらに、砲丸投、円盤投に取り組んだり、時にはリレーを走ったりするなど、高校時代に基礎を磨いたことも大きいと、北口自身も振り返っている。
鳴り物入りで日大に進学したのは、リオ五輪イヤーだった2016年。だが、その年に右肘を痛め、2年目からコーチが不在となった。肘の不安もあって心身ともに消耗し、一時期はストレスで食事が喉を通らない時期もあったという。それでもチームメイトや先輩たちの支え、そして「やり投をするために、勉強も水泳も、何もかも犠牲にして大学に来た」という強い意志が、グラウンドに足を向けさせた。
単身チェコに渡りチャンスつかむ
だが、2018年の日本選手権は、その心身の不安定を物語るものとなる。1投目に50mを超える投てきを見せながら、納得がいかずに自ら白いラインを越えてファウルに。だが、2、3投目は記録を伸ばせずに、まさかのトップ8から漏れ、4回目以降に進めなかった。北口は泣き崩れた。
その年の秋にゆっくり話す時間があった。「海外に行ってみれば?」。そんな問いに「海外(を拠点にするの)も考えていますが、どこでもいいわけじゃないですし……。難しいです」。そんな話をしながら、「今度、フィンランドで、やり投関係者が集まるカンファレンスがあるんです」。北口の運命を変える出会いは、まさにその場にあった。
懇親会の場で、ポーランドとチェコのコーチに手招きされ、「君のこと知っているよ」と世界ユースの動画を見せてきた。「走るのが遅いよ」など“指導”が入る。北口が特定の指導者がいないことを知ると、「オリンピックがあるのにどうするの?」「メダルを取りたくないの?」と矢継ぎ早に質問が飛ぶ。「取りたい。68mを投げたい」。そう返すと、「君は68mを投げられる。70mも夢じゃない」と言ってくれた。
北口はチャンスだと思った。
「もし私がコーチを頼んだら行ってもいい?」
全員「YES」と言ってくれた。その後、連絡を取り合った中で、実現したのが、シェケラックコーチのチームへの遠征。「チェコに染まるつもりで」単身渡り、1ヵ月間、みっちり基礎からやり直した。帰国してシーズンインし、迎えた2019年に日本新。東京五輪を前に、ついに大器が覚醒した瞬間だった。

誰も見たことのない世界へ
東京五輪を前に日本記録を出して以降、2度も助走を変更したが、北口にとっては「いつかはしないといけないこと」。それを聞いて6年前のことを思い出した。
2015年、名古屋の瑞穂公園陸上競技場のスタンド。その日、高校3年生だった北口は日本ジュニア選手権に出場した。優勝を決めた後の6回目。それが高校の大会で投げる最後の一投だった。
これまでとはひと味違うスピードで放たれたやりは、日本の高校生史上、最も遠くに突き刺さった。58m90。その年の7月に同学年の山下実花子(京都共栄高、現・九州共立大院)が樹立した58m59の高校記録を塗り替えた。
その直後にスタンドで話を聞いた。松橋先生から渡されたビデオカメラで自身の投げを何度も、何度も見返し、「うーん……」と首をかしげ、フィールドに視線を向ける。「まだ物足りない感じ」。納得いく投げではなかった。
その時と今の姿が重なる。どれだけ自己記録を伸ばしても、もっと遠くに投げたい、強くなりたいと思っている。目の前の結果や、オリンピックのためだけじゃない。やり投選手として、アスリートとして成長するためなら、どんな苦難でも挑戦する。
東京五輪の予選から逆算して2週間前。最後の調整として記録会に出場した。記録は57m台が1本だったが「練習の一環」であり、「練習で57mなんて投げたことがない」と笑う北口。順調そうだ。
ドーハ世界選手権では決勝進出を逃して悔し涙を流したが「もう忘れました」。あの時より強くなりたいと思って取り組んだ2年間。「体力面では確実に成長できています。あとは技術面を少しずつ調整していくだけ」。
東京五輪では「63mが勝負できるスタートライン」だと言う。予選で1本、決勝の序盤で1本、63mを投げられれば、トップ8に残って「自分の中で勝負できる」と踏んでいる。楽しければよく笑い、悔しければ子供のように泣きじゃくる。「泣かないようにね」と言うと、「それはどうかな……自信はないです」と笑った。
女子やり投で入賞すれば、1932年ロサンゼルス五輪の真保正子(4位)、36年ベルリン五輪(5位)の山本定子に続く3人目。メダルはもちろん初だ。
66mを投げてもなお、変化を求め、進化を求め、完成形はまだ見えない。「日本人が誰も見たことがない“別世界”に行きたいんです」。そう話す北口の目線は、東京五輪を通過点に、ずっとずっと遠く、はるか彼方を向いている。

文/向永拓史
 女子やり投の日本記録保持者・北口榛花(JAL)が、東京五輪・陸上競技の5日目の8月3日に登場する。世界基準のポテンシャルを誇る北口。女子ただ1人のフィールド種目代表として目指すのは「1人でも多く倒すこと」。幼い頃から夢見てきた舞台に、日本の大器がついに立つ。
女子やり投の日本記録保持者・北口榛花(JAL)が、東京五輪・陸上競技の5日目の8月3日に登場する。世界基準のポテンシャルを誇る北口。女子ただ1人のフィールド種目代表として目指すのは「1人でも多く倒すこと」。幼い頃から夢見てきた舞台に、日本の大器がついに立つ。
五輪を前に助走のリズム変更
何度も何度もスマートフォンでチェコにいるディヴィッド・シェケラックコーチから出された練習メニューを確認。離れている時はスマホやアプリを使ってコミュニケーションを取る。遠くを見つめるとき、何を考えているのか聞いてみた。 「あー、やりたくないなぁって」 北口はそう言って笑ったあと、険しい表情を浮かべ、フーッと一息ついてからまた走り出す。 2019年のシーズン終了から2度の冬季練習で、短距離ブロック顔負けくらいの時間を走る練習に費やしたという。走り終わったあと、「このメニュー、なんか違う気がする。チェコ語でメニューが出されるから合っているかわからない」とつぶやく。大変そうだけど、なんだか楽しげだ。 やり投選手とは思えない練習メニュー。そういえば、練習で投げているところをほとんど見たことがない。走り終え、クタクタになって、また空を見つめる。女子やり投日本記録保持者は、いったいどこを見ているのだろうか。 2019年の5月に64m36の日本新記録を樹立。いち早く東京五輪の参加標準記録を突破した。その年のドーハ世界選手権に初出場し、決勝まであと6cmまで迫る健闘。悔し涙を流したものの、直後の北九州カーニバルでは“世界基準”と言える66m00と再び日本記録を叩き出した。 普通であれば、この状態でオリンピックへ、となるところ。だが、コロナ禍で東京五輪が延期したこともあり、昨シーズン北口は助走の変更に踏み切った。 「もちろん延期決まったから変えたのもありますが、東京五輪でどうこうということではなくて、66mを投げたあとも『それ以上を投げるためには何かを変えないといけない』という思いはずっとありました」 2019年シーズンは16歩の助走のうち、やりを持ちながら走る「保持走」と、身体を横にして構えに入る「クロスステップ」が、8歩ずつだった。そのリズムを昨年は10歩+6歩に変更。 これまでも助走スピードが大きな課題だった北口は、「スピードを上げるために助走距離を延ばす選択肢もあるとは思いますが、分析データを見るとクロスステップで減速していたので、それならクロスを減らせば減速率を抑えられると思いました」とその狙いを明かしている。 だが、そのフォームは安定感を欠き、ある程度ハマった時は全日本実業団のように63m45をマークできたが、60m台はこの時の2本のみ。日本選手権でも連覇を逃している。
今年に入ってさらに助走を改良
「どうしてもやりを引くタイミングが毎回変わってしまって……。投げの準備に入るまでに遅れることが多かった」と、なかなか感覚をつかめずにいた。 走練習を重ねたことで助走スピードは確かに向上。だが、その反面、特長だった上半身が生かし切れない。もどかしい思いがあった。 そうしたなか、春にはシェケラックコーチがいるチェコへと渡った。コロナ禍でもちろん不安はあったが、東京五輪までにしっかりコミュニケーションを図りたかった。 チェコに着いた北口に、シェケラックコーチは「助走を変えよう」と提案する。足踏みするルーティンも「やめなさい」とストップ。「最初はめちゃくちゃ抵抗しました」と北口は笑う。だが、「私は“投げ”が特長の選手なので、そこを生かすために、投げの“準備”に入るためにクロスステップを8歩に戻しました」と受け入れた。当然、これまでとはまったく違う投げになる。 欧州で3試合に出場して1度も60mを超えられず。「このまま速く走り続けていいのかなって。ヨーロッパの選手よりも助走距離が長くて、走るのが苦手なのになんでこんなに走るの? ってコーチに聞いたりもして。焦りもありましたし、誰を信じていいのか迷いました」。それでも最後は「自分のやってきたことを信じる」と心に決めた。 帰国後、国士大競技会で59m11を投げて気持ちが吹っ切れると、日本選手権では61m49を投げて2年ぶりの優勝。東京五輪代表の切符をつかみ取った。順風満帆から一転、苦しい日々
北口は幼い頃からオリンピックを夢見てきた。バドミントンやスイミングに励んでいた少女は、「ボランティアでもどんなかたちでもオリンピックに関わりたい」という思いが幼心に芽生えていた。 北海道・旭川東高に進学してから陸上部に。中学時代、北口のバドミントン部の先輩が陸上部のマネジャーになり、当時顧問だった松橋昌巳先生に「こんな子がいます」と推薦したのがすべての始まりだった。 長身と身体能力、肩の強さと柔軟性を見込まれて、やり投の素質はすぐに花開く。当初は水泳と掛け持ちだったが、高1でインターハイに出場。陸上に専念すると、高2でインターハイを優勝し、3年時には連覇した。さらに世界ユース選手権(18歳未満)では世界一に輝いている。 どれだけ直接的な影響があるかはわからないが、北口の特徴でもある肩の柔軟性や強さは競泳やバドミントンとは無関係ではないだろう。さらに、砲丸投、円盤投に取り組んだり、時にはリレーを走ったりするなど、高校時代に基礎を磨いたことも大きいと、北口自身も振り返っている。 鳴り物入りで日大に進学したのは、リオ五輪イヤーだった2016年。だが、その年に右肘を痛め、2年目からコーチが不在となった。肘の不安もあって心身ともに消耗し、一時期はストレスで食事が喉を通らない時期もあったという。それでもチームメイトや先輩たちの支え、そして「やり投をするために、勉強も水泳も、何もかも犠牲にして大学に来た」という強い意志が、グラウンドに足を向けさせた。単身チェコに渡りチャンスつかむ
だが、2018年の日本選手権は、その心身の不安定を物語るものとなる。1投目に50mを超える投てきを見せながら、納得がいかずに自ら白いラインを越えてファウルに。だが、2、3投目は記録を伸ばせずに、まさかのトップ8から漏れ、4回目以降に進めなかった。北口は泣き崩れた。 その年の秋にゆっくり話す時間があった。「海外に行ってみれば?」。そんな問いに「海外(を拠点にするの)も考えていますが、どこでもいいわけじゃないですし……。難しいです」。そんな話をしながら、「今度、フィンランドで、やり投関係者が集まるカンファレンスがあるんです」。北口の運命を変える出会いは、まさにその場にあった。 懇親会の場で、ポーランドとチェコのコーチに手招きされ、「君のこと知っているよ」と世界ユースの動画を見せてきた。「走るのが遅いよ」など“指導”が入る。北口が特定の指導者がいないことを知ると、「オリンピックがあるのにどうするの?」「メダルを取りたくないの?」と矢継ぎ早に質問が飛ぶ。「取りたい。68mを投げたい」。そう返すと、「君は68mを投げられる。70mも夢じゃない」と言ってくれた。 北口はチャンスだと思った。 「もし私がコーチを頼んだら行ってもいい?」 全員「YES」と言ってくれた。その後、連絡を取り合った中で、実現したのが、シェケラックコーチのチームへの遠征。「チェコに染まるつもりで」単身渡り、1ヵ月間、みっちり基礎からやり直した。帰国してシーズンインし、迎えた2019年に日本新。東京五輪を前に、ついに大器が覚醒した瞬間だった。
誰も見たことのない世界へ
東京五輪を前に日本記録を出して以降、2度も助走を変更したが、北口にとっては「いつかはしないといけないこと」。それを聞いて6年前のことを思い出した。 2015年、名古屋の瑞穂公園陸上競技場のスタンド。その日、高校3年生だった北口は日本ジュニア選手権に出場した。優勝を決めた後の6回目。それが高校の大会で投げる最後の一投だった。 これまでとはひと味違うスピードで放たれたやりは、日本の高校生史上、最も遠くに突き刺さった。58m90。その年の7月に同学年の山下実花子(京都共栄高、現・九州共立大院)が樹立した58m59の高校記録を塗り替えた。 その直後にスタンドで話を聞いた。松橋先生から渡されたビデオカメラで自身の投げを何度も、何度も見返し、「うーん……」と首をかしげ、フィールドに視線を向ける。「まだ物足りない感じ」。納得いく投げではなかった。 その時と今の姿が重なる。どれだけ自己記録を伸ばしても、もっと遠くに投げたい、強くなりたいと思っている。目の前の結果や、オリンピックのためだけじゃない。やり投選手として、アスリートとして成長するためなら、どんな苦難でも挑戦する。 東京五輪の予選から逆算して2週間前。最後の調整として記録会に出場した。記録は57m台が1本だったが「練習の一環」であり、「練習で57mなんて投げたことがない」と笑う北口。順調そうだ。 ドーハ世界選手権では決勝進出を逃して悔し涙を流したが「もう忘れました」。あの時より強くなりたいと思って取り組んだ2年間。「体力面では確実に成長できています。あとは技術面を少しずつ調整していくだけ」。 東京五輪では「63mが勝負できるスタートライン」だと言う。予選で1本、決勝の序盤で1本、63mを投げられれば、トップ8に残って「自分の中で勝負できる」と踏んでいる。楽しければよく笑い、悔しければ子供のように泣きじゃくる。「泣かないようにね」と言うと、「それはどうかな……自信はないです」と笑った。 女子やり投で入賞すれば、1932年ロサンゼルス五輪の真保正子(4位)、36年ベルリン五輪(5位)の山本定子に続く3人目。メダルはもちろん初だ。 66mを投げてもなお、変化を求め、進化を求め、完成形はまだ見えない。「日本人が誰も見たことがない“別世界”に行きたいんです」。そう話す北口の目線は、東京五輪を通過点に、ずっとずっと遠く、はるか彼方を向いている。 文/向永拓史
文/向永拓史 |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking  人気記事ランキング
人気記事ランキング
2025.04.22
愛知製鋼にケニア出身の24歳サイモン・ガサ・ムンガイが加入
2025.04.22
東京世界陸上が朝日新聞社とスポンサー契約締結 報道、スポーツ支援の実績で貢献目指す
2025.04.17
駅伝王者に復権した旭化成 選手たちがパフォーマンスを最大限に発揮できた要因とは?
-
2025.04.19
-
2025.04.17
-
2025.04.20
-
2025.04.16
-
2025.04.20
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
2025.03.23
女子は長野東が7年ぶりの地元V アンカー・田畑陽菜が薫英女学院を逆転/春の高校伊那駅伝
-
2025.04.01
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.04.22
愛知製鋼にケニア出身の24歳サイモン・ガサ・ムンガイが加入
愛知製鋼は4月22日、サイモン・ガサ・ムンガイが新たに加入したとチームのSNSで発表した。 ケニア・マウセカンダリ高出身の24歳。ケニアでは昨年12月のケニアクロスカントリーシリーズ第6戦の10kmシニア男子で5位(32 […]
2025.04.22
東京世界陸上が朝日新聞社とスポンサー契約締結 報道、スポーツ支援の実績で貢献目指す
公益財団法人東京2025世界陸上財団は4月22日、朝日新聞社とスポンサー契約を締結したことを発表した。 朝日新聞社は1879年1月25日に創刊。以来、全国紙として国内外のさまざまなニュース、情報を発信してきたほか、スポー […]
2025.04.22
M&Aベストパートナーズがお披露目会!4月から選手10人で本格始動 神野大地「一枚岩になって戦っていく」
株式会社M&Aベストパートナーズは4月21日、東京都内で同社の陸上部「MABPマーヴェリック」のお披露目会を開いた。 チームは2023年12月に発足。プロランナーとして活動する青学大OBの神野大地をプレイングマネージャー […]
2025.04.21
男子4×100mR代表にサニブラウン、鵜澤飛羽、西岡尚輝らが選出! 9月の世界陸上につながる一戦/世界リレー
日本陸連は4月21日、来月行われる世界リレーの代表メンバーを発表した。 大会は男女の4×100mリレー、4×400mリレー、そして男女混合の4×400mリレーの5種目を実施。日本からは男子4×100mリレーのみを派遣する […]
Latest Issue  最新号
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)