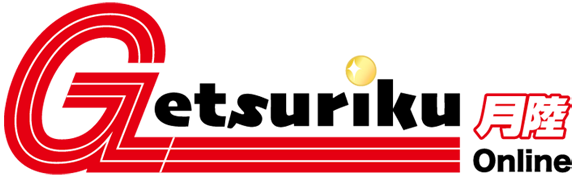2022.07.28

山梨学大の上田誠仁顧問の月陸Online特別連載コラム。これまでの経験や感じたこと、想いなど、心のままに綴っていただきます!
第23回「忘れられぬ1978年1月2日の夜~スタートラインに立てなかった君たちへ贈るエール~」
夏の強い陽射しが眩しい。
ただでさえうんざりするほどの暑さに加え、新型コロナウイルスの感染者数が再増加傾向となってきた。
振り返ると、スポーツ界は幾度となく大会の中止・延期を余儀なくされてきた。昨年開催されたスポーツの祭典、東京オリンピック・パラリンピックすらも残念ながら無観客での開催であったことは記憶に新しい。
今思い起こしても、あの熱い戦いぶりを取り囲むような大観衆の中で開催ができていればと悔やむ気持ちは、心に刻み込まれたままである。
あれから1年。徐々にスポーツ観戦も可能となり、国内の野球・サッカーなどのプロリーグも有観客で開催されるようになってきた。
先日まで米国・オレゴンで開催された世界選手権は、歴史あるヘイワード・フィールドのスタンドを埋め尽くす大観衆の中で行われた。選手たちにとって最高の舞台設定がなされたわけである。
 オレゴン世界陸上ではスタンドとの距離が近く、観客の声援が選手のパフォーマンを後押しした(観客のほとんどがノーマスクなのが気になる…)
オレゴン世界陸上ではスタンドとの距離が近く、観客の声援が選手のパフォーマンを後押しした(観客のほとんどがノーマスクなのが気になる…)
しかしながら、チームジャパンにおいてクラスター(集団感染)が発生し、選手の欠場が余儀なくされたとの報道が相次いで届いてきた。まるで背中に氷水をいきなり浴びせられたような悲しみに襲われた。
日本代表となるまでの、厳しいトレーニングを積み重ねた膨大な時間の集積と、世界の舞台で戦えるという晴れやかな舞台が、一瞬で無に帰してしまったのだ。
スポーツ選手は全力で戦った上での結果をしっかりと受け止める覚悟はできている。しかし、直前でそれすらも叶わなかった選手たちの心情を思うと胸が痛む。
男子マラソンの欠場を余儀なくされた鈴木健吾選手(富士通)を神奈川大時代に育てた大後栄治監督と、7月18日に関東学連主催の網走長距離競技会でお会いした。鈴木選手がどのように受け止めているかをうかがった。
鈴木選手は「世界選手権で今の立ち位置を確認したかった。マラソン日本記録を樹立した後、苦しい期間を乗り越えて挑んだ大会だっただけに落胆も大きい。それでも大会を迎えるにあたって良いトレーニングと良い状態でオレゴン入りができた。それは貴重なプロセスの経験ができたということなので、次のステップを踏むための財産として捉えている」と語っていたそうだ。
鈴木選手にとって初めての国際大会であり、直前でスタートラインに立つことが叶わなくなった失望は計り知れない。
そのように思いを巡らせていると、1978年1月2日の夜が思い起こされた。日本代表の鈴木選手に対して思いを重ねるには申し訳ない気もするが、私自身の一番忘れられない思い出でもあり柱となっている出来事であった。
大学1年の第54回箱根駅伝、アンカー10区でエントリーされて迎えた復路前日の夜。すでにユニフォームにはアスリートビブス「10」(箱根駅伝のゼッケンは走る区間が記載されている)を縫い付け、明日の準備も整え、付き添いとの打ち合わせも済ませて寝床で横になっていた時間だった。
突然、部屋に訪れたのは往路の4区を走り終えた長距離主将の田中登先輩。大会前日で就寝時間を過ぎているとは言え、先輩が部屋に来たからにはすぐさま起きて、来訪の理由を尋ねるとともに「明日は頑張ります」と言葉を発する。
すると、すぐさま次のような返答であった。
「あっ!お前は頑張らなくていいんだ! いましがた澤木(啓祐)監督から電話があって、上田は明日付き添いに回れということだ。アンカーは付き添い予定であった波多野に変更するそうだ。波多野にはすでに連絡済みで、すでに準備を終えて寝ている。行動予定は同じなので明日は朝練から付き添いよろしく頼むぞ!」
付き添いよろしく頼むぞといきなり言われても、自分としては全然よろしくないわけで、頭上から岩石が降り注いでくるような衝撃を受けた記憶が蘇る。
先輩が部屋を出て行った後もしばしボーゼンとしていた。連載コラム第8回で書いたように、当時は百円硬貨を利用して通話ができる公衆電話BOXしか通信手段がなかった。小銭入れを握りしめ、小雪の舞う夜更けではあったが、合宿所近くの公衆電話から香川の実家に電話をかけた。当時はまだNHKのラジオ中継しかなかったので、「郷里の家族には周波数を合わせても自分は走っていないことを告げておかねば」との思いだった。
選手を外された心情的には「何も前日のこの時間に、しかも伝達で告げることはないのに……」。中学時代から見てきた青春ドラマのワンシーンならば、数日前に監督にグラウンドや別室に呼び出され、起用しない理由や次回に向けての励ましやらアドバイスがあっても良さそうなものだ。
しかし、現実には「お前は頑張らなくていいんだ!」の一言。「それはないだろう……」。と自分の至らなさを棚に上げて、悪態の一つや二つは叫びそうであった。
電話口に出た父から、「監督が起用しないというからにはそれなりの理由があるはずだ、よくよく振り返って考えてみろ!」と厳しく嗜められた。その後は惨めさと情けなさで、どのような話をしたか記憶にはない。気がつけば涙を流しながら受話器を握りしめ、最後の百円硬貨が電話機に飲み込まれ、通話終了の「プー」という不通音に切り替わっていた。
重要なのは先ほど棚に上げたことだったのだ。
当時の箱根駅伝は、10区間の選手を入れて捕員4名を含む14名を12月14日にエントリーするルールであった。アンカーにエントリーされた喜びも束の間、不安と重圧が入り交じる日々を送ることとなった。
そんな思いが心に湧き上がると、溜息をついてしまう。その溜息をついてしまうと体調が上がらない場所が三つある。食卓と風呂と寝床である。
思えば、大会前にはその場所で溜息ばかりついていた気がした。「あの時にもう少しこうしておけばよかった、ああしておけばよかった」という後悔の溜息である。故障気味で入学した私は、陸上競技に対する集中力が細くなった時期があった。できなかったことではなく、やらなかったこととやろうとしなかったことが溜息の原因であった。
変えることのできない過去であるはずなのに、悔やむことを後悔というならば、まさに大会前日の寝床の中で大きな溜息を抱えて横たわっていた私のことであった。「お前は頑張らなくていいんだ!」と告げるように指示を出した監督のコーチングはまさに的を射ていたのである。
そのお陰で翌日は、悔しさと惨めさを抱えつつもアンカーの付き添いをし、その後ゴールへと先回りして選手を迎えた。大会後は郷里への帰省を取りやめ、頭髪を高校時代のようにバリカンで丸めてチャンネルを切り替えていた。
少し髪が伸びた頃には波多野君の背中を見ないで走れるようになろう、そして夏の合宿では4年生エースの背中に食らいついて行けるようになろうと頑張れた。あの日の夜についた溜息はこれからの取り組みで消し去るしかないと思えたからだ。
そのお陰もあって、翌年55回大会では山上りの5区を区間1位で駆け上がり、総合優勝に貢献できた。
そのような思い出を呼び起こしてくれた場所があった。
時は現代へ戻り、先日、報知新聞創刊150周年記念の報道写真展「瞬間の記憶」が恵比寿の東京都写真美術館で開催されているというご案内を受けた。
報知新聞は箱根駅伝創設に関わった金栗四三氏の依頼を受けて第1回大会開催に尽力していただき、現在も大会の後援をしていただいていることから、先日展示を拝見させていただいた。

箱根駅伝のコーナーに55回大会の芦ノ湖にゴールする瞬間の写真を展示していただいていた。その写真を見るにつけ、瞬間の記憶がフラッシュバックのように蘇った。あの歓喜の背景には1年前のあの指導と嗜め、そして大会を迎えるまでのプロセスの経験があったからこそと、思い起こす事ができたからだ。
話は戻るが、鈴木選手は7月26日現在もオレゴンで隔離中であるが、体調も回復し、次の目標に向かう気持ちであることを大後監督からお聞きした。ぜひとも、変えることのできない過去を悔やむよりも、しっかりと前を向いてまた頑張ってほしいと願っている。
今回のコロナ感染に泣いた選手に励ましのエールをこめて贈りたい。
追記
54回大会後日談。
1977年12月14日のエントリーを終えた日に、箱根当日は波多野選手で行くと、本人と当時駅伝主務であった山本康隆さんには伝えられていたそうだ。大会が近づいても選手変更について本人(私)には伝えられていない様子だったので、山本さんは心配になり、澤木監督に「いつ上田君に選手変更を告げるのですか」と尋ねたそうだ。
澤木監督は「上田にとって一番効果的な、しかるべき時に通告する。心配するな」とのことだったらしい。
しかるべき時というのが前日の夜就寝後だったわけである。お陰で私は後悔の溜息を「これからの取組み」としてやる気スイッチが入ったということだった。
コーチングとはかくあるべきであろう。
| 上田誠仁 Ueda Masahito/1959年生まれ、香川県出身。山梨学院大学スポーツ科学部スポーツ科学科教授。順天堂大学時代に3年連続で箱根駅伝の5区を担い、2年時と3年時に区間賞を獲得。2度の総合優勝に貢献した。卒業後は地元・香川県内の中学・高校教諭を歴任。中学教諭時代の1983年には日本選手権5000mで2位と好成績を収めている。85年に山梨学院大学の陸上競技部監督へ就任し、92年には創部7年、出場6回目にして箱根駅伝総合優勝を達成。以降、出雲駅伝5連覇、箱根総合優勝3回など輝かしい実績を誇るほか、中村祐二や尾方剛、大崎悟史、井上大仁など、のちにマラソンで世界へ羽ばたく選手を多数育成している。2022年4月より山梨学院大学陸上競技部顧問に就任。 |
 山梨学大の上田誠仁顧問の月陸Online特別連載コラム。これまでの経験や感じたこと、想いなど、心のままに綴っていただきます!
山梨学大の上田誠仁顧問の月陸Online特別連載コラム。これまでの経験や感じたこと、想いなど、心のままに綴っていただきます!
第23回「忘れられぬ1978年1月2日の夜~スタートラインに立てなかった君たちへ贈るエール~」
夏の強い陽射しが眩しい。 ただでさえうんざりするほどの暑さに加え、新型コロナウイルスの感染者数が再増加傾向となってきた。 振り返ると、スポーツ界は幾度となく大会の中止・延期を余儀なくされてきた。昨年開催されたスポーツの祭典、東京オリンピック・パラリンピックすらも残念ながら無観客での開催であったことは記憶に新しい。 今思い起こしても、あの熱い戦いぶりを取り囲むような大観衆の中で開催ができていればと悔やむ気持ちは、心に刻み込まれたままである。 あれから1年。徐々にスポーツ観戦も可能となり、国内の野球・サッカーなどのプロリーグも有観客で開催されるようになってきた。 先日まで米国・オレゴンで開催された世界選手権は、歴史あるヘイワード・フィールドのスタンドを埋め尽くす大観衆の中で行われた。選手たちにとって最高の舞台設定がなされたわけである。 オレゴン世界陸上ではスタンドとの距離が近く、観客の声援が選手のパフォーマンを後押しした(観客のほとんどがノーマスクなのが気になる…)
しかしながら、チームジャパンにおいてクラスター(集団感染)が発生し、選手の欠場が余儀なくされたとの報道が相次いで届いてきた。まるで背中に氷水をいきなり浴びせられたような悲しみに襲われた。
日本代表となるまでの、厳しいトレーニングを積み重ねた膨大な時間の集積と、世界の舞台で戦えるという晴れやかな舞台が、一瞬で無に帰してしまったのだ。
スポーツ選手は全力で戦った上での結果をしっかりと受け止める覚悟はできている。しかし、直前でそれすらも叶わなかった選手たちの心情を思うと胸が痛む。
男子マラソンの欠場を余儀なくされた鈴木健吾選手(富士通)を神奈川大時代に育てた大後栄治監督と、7月18日に関東学連主催の網走長距離競技会でお会いした。鈴木選手がどのように受け止めているかをうかがった。
鈴木選手は「世界選手権で今の立ち位置を確認したかった。マラソン日本記録を樹立した後、苦しい期間を乗り越えて挑んだ大会だっただけに落胆も大きい。それでも大会を迎えるにあたって良いトレーニングと良い状態でオレゴン入りができた。それは貴重なプロセスの経験ができたということなので、次のステップを踏むための財産として捉えている」と語っていたそうだ。
鈴木選手にとって初めての国際大会であり、直前でスタートラインに立つことが叶わなくなった失望は計り知れない。
そのように思いを巡らせていると、1978年1月2日の夜が思い起こされた。日本代表の鈴木選手に対して思いを重ねるには申し訳ない気もするが、私自身の一番忘れられない思い出でもあり柱となっている出来事であった。
大学1年の第54回箱根駅伝、アンカー10区でエントリーされて迎えた復路前日の夜。すでにユニフォームにはアスリートビブス「10」(箱根駅伝のゼッケンは走る区間が記載されている)を縫い付け、明日の準備も整え、付き添いとの打ち合わせも済ませて寝床で横になっていた時間だった。
突然、部屋に訪れたのは往路の4区を走り終えた長距離主将の田中登先輩。大会前日で就寝時間を過ぎているとは言え、先輩が部屋に来たからにはすぐさま起きて、来訪の理由を尋ねるとともに「明日は頑張ります」と言葉を発する。
すると、すぐさま次のような返答であった。
「あっ!お前は頑張らなくていいんだ! いましがた澤木(啓祐)監督から電話があって、上田は明日付き添いに回れということだ。アンカーは付き添い予定であった波多野に変更するそうだ。波多野にはすでに連絡済みで、すでに準備を終えて寝ている。行動予定は同じなので明日は朝練から付き添いよろしく頼むぞ!」
付き添いよろしく頼むぞといきなり言われても、自分としては全然よろしくないわけで、頭上から岩石が降り注いでくるような衝撃を受けた記憶が蘇る。
先輩が部屋を出て行った後もしばしボーゼンとしていた。連載コラム第8回で書いたように、当時は百円硬貨を利用して通話ができる公衆電話BOXしか通信手段がなかった。小銭入れを握りしめ、小雪の舞う夜更けではあったが、合宿所近くの公衆電話から香川の実家に電話をかけた。当時はまだNHKのラジオ中継しかなかったので、「郷里の家族には周波数を合わせても自分は走っていないことを告げておかねば」との思いだった。
選手を外された心情的には「何も前日のこの時間に、しかも伝達で告げることはないのに……」。中学時代から見てきた青春ドラマのワンシーンならば、数日前に監督にグラウンドや別室に呼び出され、起用しない理由や次回に向けての励ましやらアドバイスがあっても良さそうなものだ。
しかし、現実には「お前は頑張らなくていいんだ!」の一言。「それはないだろう……」。と自分の至らなさを棚に上げて、悪態の一つや二つは叫びそうであった。
電話口に出た父から、「監督が起用しないというからにはそれなりの理由があるはずだ、よくよく振り返って考えてみろ!」と厳しく嗜められた。その後は惨めさと情けなさで、どのような話をしたか記憶にはない。気がつけば涙を流しながら受話器を握りしめ、最後の百円硬貨が電話機に飲み込まれ、通話終了の「プー」という不通音に切り替わっていた。
重要なのは先ほど棚に上げたことだったのだ。
当時の箱根駅伝は、10区間の選手を入れて捕員4名を含む14名を12月14日にエントリーするルールであった。アンカーにエントリーされた喜びも束の間、不安と重圧が入り交じる日々を送ることとなった。
そんな思いが心に湧き上がると、溜息をついてしまう。その溜息をついてしまうと体調が上がらない場所が三つある。食卓と風呂と寝床である。
思えば、大会前にはその場所で溜息ばかりついていた気がした。「あの時にもう少しこうしておけばよかった、ああしておけばよかった」という後悔の溜息である。故障気味で入学した私は、陸上競技に対する集中力が細くなった時期があった。できなかったことではなく、やらなかったこととやろうとしなかったことが溜息の原因であった。
変えることのできない過去であるはずなのに、悔やむことを後悔というならば、まさに大会前日の寝床の中で大きな溜息を抱えて横たわっていた私のことであった。「お前は頑張らなくていいんだ!」と告げるように指示を出した監督のコーチングはまさに的を射ていたのである。
そのお陰で翌日は、悔しさと惨めさを抱えつつもアンカーの付き添いをし、その後ゴールへと先回りして選手を迎えた。大会後は郷里への帰省を取りやめ、頭髪を高校時代のようにバリカンで丸めてチャンネルを切り替えていた。
少し髪が伸びた頃には波多野君の背中を見ないで走れるようになろう、そして夏の合宿では4年生エースの背中に食らいついて行けるようになろうと頑張れた。あの日の夜についた溜息はこれからの取り組みで消し去るしかないと思えたからだ。
そのお陰もあって、翌年55回大会では山上りの5区を区間1位で駆け上がり、総合優勝に貢献できた。
そのような思い出を呼び起こしてくれた場所があった。
時は現代へ戻り、先日、報知新聞創刊150周年記念の報道写真展「瞬間の記憶」が恵比寿の東京都写真美術館で開催されているというご案内を受けた。
報知新聞は箱根駅伝創設に関わった金栗四三氏の依頼を受けて第1回大会開催に尽力していただき、現在も大会の後援をしていただいていることから、先日展示を拝見させていただいた。
オレゴン世界陸上ではスタンドとの距離が近く、観客の声援が選手のパフォーマンを後押しした(観客のほとんどがノーマスクなのが気になる…)
しかしながら、チームジャパンにおいてクラスター(集団感染)が発生し、選手の欠場が余儀なくされたとの報道が相次いで届いてきた。まるで背中に氷水をいきなり浴びせられたような悲しみに襲われた。
日本代表となるまでの、厳しいトレーニングを積み重ねた膨大な時間の集積と、世界の舞台で戦えるという晴れやかな舞台が、一瞬で無に帰してしまったのだ。
スポーツ選手は全力で戦った上での結果をしっかりと受け止める覚悟はできている。しかし、直前でそれすらも叶わなかった選手たちの心情を思うと胸が痛む。
男子マラソンの欠場を余儀なくされた鈴木健吾選手(富士通)を神奈川大時代に育てた大後栄治監督と、7月18日に関東学連主催の網走長距離競技会でお会いした。鈴木選手がどのように受け止めているかをうかがった。
鈴木選手は「世界選手権で今の立ち位置を確認したかった。マラソン日本記録を樹立した後、苦しい期間を乗り越えて挑んだ大会だっただけに落胆も大きい。それでも大会を迎えるにあたって良いトレーニングと良い状態でオレゴン入りができた。それは貴重なプロセスの経験ができたということなので、次のステップを踏むための財産として捉えている」と語っていたそうだ。
鈴木選手にとって初めての国際大会であり、直前でスタートラインに立つことが叶わなくなった失望は計り知れない。
そのように思いを巡らせていると、1978年1月2日の夜が思い起こされた。日本代表の鈴木選手に対して思いを重ねるには申し訳ない気もするが、私自身の一番忘れられない思い出でもあり柱となっている出来事であった。
大学1年の第54回箱根駅伝、アンカー10区でエントリーされて迎えた復路前日の夜。すでにユニフォームにはアスリートビブス「10」(箱根駅伝のゼッケンは走る区間が記載されている)を縫い付け、明日の準備も整え、付き添いとの打ち合わせも済ませて寝床で横になっていた時間だった。
突然、部屋に訪れたのは往路の4区を走り終えた長距離主将の田中登先輩。大会前日で就寝時間を過ぎているとは言え、先輩が部屋に来たからにはすぐさま起きて、来訪の理由を尋ねるとともに「明日は頑張ります」と言葉を発する。
すると、すぐさま次のような返答であった。
「あっ!お前は頑張らなくていいんだ! いましがた澤木(啓祐)監督から電話があって、上田は明日付き添いに回れということだ。アンカーは付き添い予定であった波多野に変更するそうだ。波多野にはすでに連絡済みで、すでに準備を終えて寝ている。行動予定は同じなので明日は朝練から付き添いよろしく頼むぞ!」
付き添いよろしく頼むぞといきなり言われても、自分としては全然よろしくないわけで、頭上から岩石が降り注いでくるような衝撃を受けた記憶が蘇る。
先輩が部屋を出て行った後もしばしボーゼンとしていた。連載コラム第8回で書いたように、当時は百円硬貨を利用して通話ができる公衆電話BOXしか通信手段がなかった。小銭入れを握りしめ、小雪の舞う夜更けではあったが、合宿所近くの公衆電話から香川の実家に電話をかけた。当時はまだNHKのラジオ中継しかなかったので、「郷里の家族には周波数を合わせても自分は走っていないことを告げておかねば」との思いだった。
選手を外された心情的には「何も前日のこの時間に、しかも伝達で告げることはないのに……」。中学時代から見てきた青春ドラマのワンシーンならば、数日前に監督にグラウンドや別室に呼び出され、起用しない理由や次回に向けての励ましやらアドバイスがあっても良さそうなものだ。
しかし、現実には「お前は頑張らなくていいんだ!」の一言。「それはないだろう……」。と自分の至らなさを棚に上げて、悪態の一つや二つは叫びそうであった。
電話口に出た父から、「監督が起用しないというからにはそれなりの理由があるはずだ、よくよく振り返って考えてみろ!」と厳しく嗜められた。その後は惨めさと情けなさで、どのような話をしたか記憶にはない。気がつけば涙を流しながら受話器を握りしめ、最後の百円硬貨が電話機に飲み込まれ、通話終了の「プー」という不通音に切り替わっていた。
重要なのは先ほど棚に上げたことだったのだ。
当時の箱根駅伝は、10区間の選手を入れて捕員4名を含む14名を12月14日にエントリーするルールであった。アンカーにエントリーされた喜びも束の間、不安と重圧が入り交じる日々を送ることとなった。
そんな思いが心に湧き上がると、溜息をついてしまう。その溜息をついてしまうと体調が上がらない場所が三つある。食卓と風呂と寝床である。
思えば、大会前にはその場所で溜息ばかりついていた気がした。「あの時にもう少しこうしておけばよかった、ああしておけばよかった」という後悔の溜息である。故障気味で入学した私は、陸上競技に対する集中力が細くなった時期があった。できなかったことではなく、やらなかったこととやろうとしなかったことが溜息の原因であった。
変えることのできない過去であるはずなのに、悔やむことを後悔というならば、まさに大会前日の寝床の中で大きな溜息を抱えて横たわっていた私のことであった。「お前は頑張らなくていいんだ!」と告げるように指示を出した監督のコーチングはまさに的を射ていたのである。
そのお陰で翌日は、悔しさと惨めさを抱えつつもアンカーの付き添いをし、その後ゴールへと先回りして選手を迎えた。大会後は郷里への帰省を取りやめ、頭髪を高校時代のようにバリカンで丸めてチャンネルを切り替えていた。
少し髪が伸びた頃には波多野君の背中を見ないで走れるようになろう、そして夏の合宿では4年生エースの背中に食らいついて行けるようになろうと頑張れた。あの日の夜についた溜息はこれからの取り組みで消し去るしかないと思えたからだ。
そのお陰もあって、翌年55回大会では山上りの5区を区間1位で駆け上がり、総合優勝に貢献できた。
そのような思い出を呼び起こしてくれた場所があった。
時は現代へ戻り、先日、報知新聞創刊150周年記念の報道写真展「瞬間の記憶」が恵比寿の東京都写真美術館で開催されているというご案内を受けた。
報知新聞は箱根駅伝創設に関わった金栗四三氏の依頼を受けて第1回大会開催に尽力していただき、現在も大会の後援をしていただいていることから、先日展示を拝見させていただいた。
 箱根駅伝のコーナーに55回大会の芦ノ湖にゴールする瞬間の写真を展示していただいていた。その写真を見るにつけ、瞬間の記憶がフラッシュバックのように蘇った。あの歓喜の背景には1年前のあの指導と嗜め、そして大会を迎えるまでのプロセスの経験があったからこそと、思い起こす事ができたからだ。
話は戻るが、鈴木選手は7月26日現在もオレゴンで隔離中であるが、体調も回復し、次の目標に向かう気持ちであることを大後監督からお聞きした。ぜひとも、変えることのできない過去を悔やむよりも、しっかりと前を向いてまた頑張ってほしいと願っている。
今回のコロナ感染に泣いた選手に励ましのエールをこめて贈りたい。
追記
54回大会後日談。
1977年12月14日のエントリーを終えた日に、箱根当日は波多野選手で行くと、本人と当時駅伝主務であった山本康隆さんには伝えられていたそうだ。大会が近づいても選手変更について本人(私)には伝えられていない様子だったので、山本さんは心配になり、澤木監督に「いつ上田君に選手変更を告げるのですか」と尋ねたそうだ。
澤木監督は「上田にとって一番効果的な、しかるべき時に通告する。心配するな」とのことだったらしい。
しかるべき時というのが前日の夜就寝後だったわけである。お陰で私は後悔の溜息を「これからの取組み」としてやる気スイッチが入ったということだった。
コーチングとはかくあるべきであろう。
箱根駅伝のコーナーに55回大会の芦ノ湖にゴールする瞬間の写真を展示していただいていた。その写真を見るにつけ、瞬間の記憶がフラッシュバックのように蘇った。あの歓喜の背景には1年前のあの指導と嗜め、そして大会を迎えるまでのプロセスの経験があったからこそと、思い起こす事ができたからだ。
話は戻るが、鈴木選手は7月26日現在もオレゴンで隔離中であるが、体調も回復し、次の目標に向かう気持ちであることを大後監督からお聞きした。ぜひとも、変えることのできない過去を悔やむよりも、しっかりと前を向いてまた頑張ってほしいと願っている。
今回のコロナ感染に泣いた選手に励ましのエールをこめて贈りたい。
追記
54回大会後日談。
1977年12月14日のエントリーを終えた日に、箱根当日は波多野選手で行くと、本人と当時駅伝主務であった山本康隆さんには伝えられていたそうだ。大会が近づいても選手変更について本人(私)には伝えられていない様子だったので、山本さんは心配になり、澤木監督に「いつ上田君に選手変更を告げるのですか」と尋ねたそうだ。
澤木監督は「上田にとって一番効果的な、しかるべき時に通告する。心配するな」とのことだったらしい。
しかるべき時というのが前日の夜就寝後だったわけである。お陰で私は後悔の溜息を「これからの取組み」としてやる気スイッチが入ったということだった。
コーチングとはかくあるべきであろう。
| 上田誠仁 Ueda Masahito/1959年生まれ、香川県出身。山梨学院大学スポーツ科学部スポーツ科学科教授。順天堂大学時代に3年連続で箱根駅伝の5区を担い、2年時と3年時に区間賞を獲得。2度の総合優勝に貢献した。卒業後は地元・香川県内の中学・高校教諭を歴任。中学教諭時代の1983年には日本選手権5000mで2位と好成績を収めている。85年に山梨学院大学の陸上競技部監督へ就任し、92年には創部7年、出場6回目にして箱根駅伝総合優勝を達成。以降、出雲駅伝5連覇、箱根総合優勝3回など輝かしい実績を誇るほか、中村祐二や尾方剛、大崎悟史、井上大仁など、のちにマラソンで世界へ羽ばたく選手を多数育成している。2022年4月より山梨学院大学陸上競技部顧問に就任。 |
|
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking  人気記事ランキング
人気記事ランキング
2024.11.22
田中希実が来季『グランドスラム・トラック』参戦決定!マイケル・ジョンソン氏が新設
2024.11.21
早大競走部駅伝部門が麹を活用した食品・飲料を手がける「MURO」とスポンサー契約締結
2024.11.21
立迫志穂が調整不良のため欠場/防府読売マラソン
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.17
不破聖衣来が香港で10kmレースに出場 9位でフィニッシュ
2024.11.20
【箱根駅伝2025名鑑】早稲田大学
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
-
2024.11.20
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
2024.11.07
アシックスから軽量で反発性に優れたランニングシューズ「NOVABLAST 5」が登場!
-
2024.10.27
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.22
田中希実が来季『グランドスラム・トラック』参戦決定!マイケル・ジョンソン氏が新設
来春、開幕する陸上リーグ「グランドスラム・トラック」の“レーサー”として、女子中長距離の田中希実(New Balance)が契約したと発表された。 同大会は1990年代から2000年代に男子短距離で活躍したマイケル・ジョ […]
2024.11.21
早大競走部駅伝部門が麹を活用した食品・飲料を手がける「MURO」とスポンサー契約締結
11月21日、株式会社コラゾンは同社が展開する麹専門ブランド「MURO」を通じて、早大競走部駅伝部とスポンサー契約を結んだことを発表した。 コラゾン社は「MURO」の商品である「KOJI DRINK A」および「KOJI […]
2024.11.21
立迫志穂が調整不良のため欠場/防府読売マラソン
第55回防府読売マラソン大会事務局は、女子招待選手の立迫志穂(天満屋)が欠場すると発表した。調整不良のためとしている。 立迫は今年2月の全日本実業団ハーフマラソンで1時間11分16秒の11位。7月には5000m(15分3 […]
2024.11.20
M&Aベストパートナーズに中大・山平怜生、城西大・栗原直央、國學院大・板垣俊佑が内定!神野「チーム一丸」
神野大地が選手兼監督を務めるM&Aベストパートナーズが来春入社選手として、中大・山平怜生、國學院大・板垣俊佑、城西大・栗原直央の3人が内定した。神野が自身のSNSで内定式の様子を伝えている。 山平は宮城・仙台育英 […]
2024.11.20
第101回(2025年)箱根駅伝 出場チーム選手名鑑
・候補選手は各チームが選出 ・情報は11月20日時点、チーム提供および編集部把握の公認記録を掲載 ・選手名の一部漢字で対応外のものは新字で掲載しています ・過去箱根駅伝成績で関東学生連合での出場選手は相当順位を掲載 ・一 […]
Latest Issue  最新号
最新号

2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会